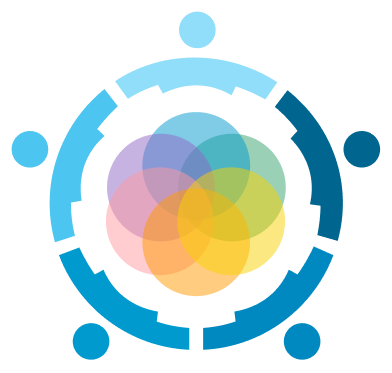M-CHAT(Modified Checklist for Autism in Toddlers; 乳幼児期自閉症チェックリスト修正版)
はじめに
発達障害のある子どもは、乳幼児期の早い段階からその子のニーズに合った遊びや学びなどの経験を通して、その子の強みを最大限に伸ばし、はりあいのある生活を送ることができます。発達障害とひとくくりに言っても、知的な遅れ、言語の障害、自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、不器用、学習障害などのさまざまな症候群がありますが、たいていそのうちいずれかの特徴を持つ子どもは複数の症候群の特徴を持っています。そのため、一人ひとり支援ニーズは異なりますが、共通して言えるのは、できるだけ早期から子どもとその家族を支援することが大切になります。
発達障害のなかで自閉スペクトラム症(ASD)については、乳幼児期にみられる早期兆候と早期から始める療育の有効性に関するエビデンスがたくさん蓄積されています。わが国では、まだASDの診療ガイドラインは存在しませんが、海外の国レベル、学会レベルでのASDの診療ガイドラインでは早期診断と早期療育(家族支援を含む)の重要性を強調しています1,2)。日本においては、残念ながら、発達障害の専門機関や専門的な訓練を受けた人材はまだ不足しています。そうした現状がありながらも、地域内の医療、保健、福祉、教育との連携ネットワークの構築、そして地域内のかかりつけ医と専門医療機関との効率的な連携に向けて取り組み始めた自治体は徐々に増えてきました。
早期からの支援には、それに先立つ気づきと早期診断が必要です。1歳6ヶ月健診では非常に多くの子どもに対応するため、家庭での様子を含め、子どもの発達状況を把握するのに十分な時間が確保できない現状があります。そのため、気づかずスルーしてしまったり、疑いを持っても診断に確信が持てず、「様子をみましょう」と対応を後延ばしにしてしまうこともあるかもしれません。かかりつけ医や保健師など最初に気づける立場にある医療・保健の専門家は、自身の経験だけに頼るのではなく、エビデンスのあるスクリーニング尺度を用いることで、その子どもが単に経過をみていてよいのか、あるいはすみやかに専門機関に紹介する必要があるのかについて、根拠を持って初期的な判断をすることができます。わが国では、確定診断が受けられない段階でも、診断前支援を受けることができる制度があり、その子どもが必要としている支援を早く受けるためには、日本の地域データに裏打ちされた発達チェックが重要です。
このコンテンツでは、日本および世界各国でのエビデンスの蓄積されたASDのスクリーニング尺度であるM-CHATについてご紹介しています。
註)M-CHATは平成30年度の診療報酬改定により、新たに認知機能検査その他の心理検査80点として保険収載されました。
- National Institute for Health and Clinical Excellence: Clinical guideline Autism in under 19s: recognition, referral and diagnosis. September 2011;
http://www.nice.org.uk/guidance/cg128/resources/autism-in-under-19s-recognition-referral-and-diagnosis-35109456621253(This link leads to an English website.) - Volkmar F et al.: Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with autism spectrum disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 53(2):237-257, 2014.
このコンテンツで紹介する内容は、以下の助成を受けて行った研究成果にもとづくものです。
- 平成16年度厚生労働科学研究費補助金(子ども家庭総合研究事業)研究課題名「乳幼児健康診査における高機能広汎性発達障害の早期評価及び地域支援のマニュアル開発に関する研究」. (課題番号H16—子ども-018)(主任研究者 神尾陽子).
- 平成16-21年度独立行政法人科学技術振興機構社会技術研究開発センタ―「脳科学と社会」研究開発領域研究開発プログラム「脳科学と教育」(タイプⅡ)研究開発プロジェクト「社会性の発達メカニズムの解明:自閉症スペクトラムと定型発達のコホート研究」(研究代表者 神尾陽子).
- 平成20‐22年度厚生労働科学研究費補助金(こころの健康科学研究事業)「1歳からの広汎性発達障害の出現とその発達的変化:地域ベースの横断的および縦断的研究」(研究代表者 神尾陽子).
M-CHATとは
エビデンスに裏付けられたASDのスクリーニング尺度
今日、幼児を対象とするASDスクリーニング尺度は多数開発されていますが、ごく一部を除く多くの尺度は、すでに診断がついている子どもと定型発達の子どもを調べて、ASD児でスクリーニング結果が陽性になることを確認するにとどまっています。しかしながら、健診など診断がついていない子どもが大多数である一般集団を対象に用いる場合、その尺度の精度(後に確定される診断を正確に予測するかどうか)を知るには、大人数を長期間フォローして実際に後の診断を確認しなくてはなりません。これは大変な労力を要する作業ですが、本コンテンツでご紹介するM-CHATは、国内外においてこうした検証作業を経て尺度の妥当性が示されたスクリーニング尺度です。スクリーニングは質問する側も答える側も一定の負担が生じますので、エビデンスに裏付けられた尺度を適切に選ぶことはとても大切です。
M-CHAT(Modified Checklist for Autism in Toddlers; 乳幼児期自閉症チェックリスト修正版)は、英国でBaron-Cohenらによって開発されたCHAT(Checklist for Autism in Toddlers; 乳幼児期自閉症チェックリスト)をもとにして、米国のRobinsやFeinらの研究チームが修正を加えて開発した、16-30ヵ月児を対象とする質問紙です1)。質問項目は、社会的発達に関する項目が16個、ASDに独特の知覚反応や常同行動に関する項目が4個、言語理解に関する項目が1個、全23項目から成り、親にはい/いいえの二択で回答してもらうものです。
詳細は、オリジナルのホームページをご参照ください。 http://mchatscreen.com/(This link leads to an English website.)
ASD の早期兆候に気づくことは、乳幼児期の社会的発達を知ること
M-CHAT項目の大部分は、社会性の発達状況を尋ねる内容です。乳幼児期の発達はことばが出ているかどうかが注目されがちですが、ことばが出る前の乳幼児は視線、指さしなど身体全体を使って親とコミュニケーションをとっています。そして、1 歳過ぎの定型発達児にはっきりと芽生えているこうした社会的行動は、後にASD と診断される子どもにはまったくみられない、あるいはあまりみられないことがほとんどです。ないはずの異常な行動がある、ということに気づくことより、“あるべき行動がない、ということに気づくのは、たくさんのこの年齢の定型発達児を熟知していないととても難しいのです。M-CHATは、月齢や発達水準にみあった社会性のマイルストーンを達成しているかどうかを確認していると言うことができます。
正確なスクリーニングには2度面接することが大切
研究から、最初にM-CHAT質問紙に回答してもらいます。カットオフを超えた場合、すぐに結論をだすよりも、1,2ヵ月後にフォローアップ面接を行う2段階方式の方が精度が高いことがわかっています。推奨されています。スクリーニングである以上、100%正確とはいきませんが、2段階方式の方がASDでないのにASDを疑って介入する“偽陽性”ケースが少なくなるからです。ただし、米国の大規模研究3)によると、こうした偽陽性ケースのほとんどがなんらかの発達の問題を有するケースで、こうしたなんらかの発達支援を要する子どもを対象とした場合、その陽性的中率は98%と高い数値が報告されています。
- Robins DL, Fein D, Barton ML et al(This link leads to an English website.): The Modified Checklist for Autism in Toddlers: an initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. J Autism Dev Disord 31: 131-144, 2001.
- Zwaigenbaum L et al.: Early screening of autism spectrum disorder: Recommendations for practice and research. Pediatrics 136(Suppl 1):S41-59, 2015.
- Chlebowski C, Robins DL, Barton ML et al. Large-scale use of the Modified Checklist for Autism in low-risk toddlers. Pediatrics 2013; 131 (4), e1121-e1127.
日本版M-CHAT(M-CHAT-JV)の使用の際の留意点
オリジナル版1)との違いは、日本版質問紙には、質問の意図が伝わりやすいように、原版にはない絵を追加しています2)。
Translations of M-CHAT - M-CHAT™ (mchatscreen.com)(This link leads to an English website.)
適用年齢は?
日本語版の健診用(1次)スクリーニングとしての適用年齢は18ヵ月を想定しています。ただし、クリニックなどでの2次スクリーニングとしては2歳まで適用可能です。米国原版は16ヵ月から30 ヵ月としており、海外の報告の多くは18から24ヵ月まで適用されているようです。本検査はスクリーニングという目的とは別に、0歳代からも社会的行動の発達状況を確認するためにも用いることもできます3)。
どのように使ったらよいのか?
1次スクリーニングとして1歳6ヵ月健診乳幼児健診で受診児全員に対して行う際には、従来の全般的発達スクリーニングと併用してください。陽性ケースの絞り込みは2段階に分けて行い、第1段階陽性ケースには1,2ヵ月間後に第2段階としてフォローアップ面接を実施することをおすすめします。マンパワーが十分すぎるほどあるのならば、気になる子どもをすべてフォローすることもできるかもしれませんが、現実的にはエビデンスに裏付けられた範囲でフォローして支援につなげる方法を選ばざるをえないからです。
フォローアップの際は、添付の面接用マニュアルを参考に、不通過項目を中心に発達状況をできるだけ具体的に確認しましょう。2段階を経てなお陽性(M-CHAT陽性)のケースは、精査をしてください(そのうえで早期支援のための窓口に紹介しましょう)。もちろん第1段階で明らかにASDが疑われるケースでは、フォローアップまで待つ必要はありません。
CARSやADOS-2などが時間をかけた行動観察をベースに専門家が行う診断補助検査であるのに対し、本検査は日常を良く知る親からの回答をベースとするスクリーニングを目的としたツールであり、ASD診断のためのツールではないことを確認しておきます。
親回答からは有益な情報が得られる一方で、専門家の観察とのギャップがありうるのも事実です。そのため、健診という限られた場面でも観察可能な行動をチェックしておくことをおすすめします。項目8「機能的遊び」、項目10「アイコンタクト」、項目13「模倣」、項目14「呼名反応」、項目15「指さし追従」は、親との面談の際に、手元におもちゃなどを用意しておくことで、実際に専門家が子どもとかかわって確認することがしやすい項目です。こうすることで、親の気づきが薄い場合でも、育児支援につなげやすくなりますので、これらの項目では観察者の判断を採用することが望ましいです。
M-CHATは信頼できるのか?
既存のASD早期スクリーニング検査のうちM-CHATのみ、1次、2次スクリーニングとも強いエビデンスが報告されています4)。
日本語版についても、信頼性と妥当性は検証済みです。たとえば、信頼性は父親―母親間信頼性は0.933、再検査信頼性は0.990、CARSとの基準関連妥当性は0.581と報告されています2)。
1歳6ヵ月健診における有用性についても複数の地域で長期追跡を行った結果からエビデンスが得られています5)。2段階で実施したASDの感度は0.613、特異度は0.985、陽性的中率は43-46%、すなわち陽性者2人に1人は後にASDと診断されることを報告しています(この調査ではM-CHAT陽性で、後にASDと確定されなかったケースについてもASD閾下あるいは何らかの発達支援ニーズがあることが確認されています)。
通過・不通過の基準は?(M-CHATスコアリングシート参照のこと)
3項目基準をおすすめします。3項目基準とは、
- 第1段階:全23項目中3項目以上で不通過であれば要フォローアップ
- 第2段階フォローアップ:依然、全23項目中3項目で不通過であれば陽性
とするものです。スコアリングシートの回答欄にある〇を重ねていただくと、重なる項目数が3つ以上あれば、陽性(不通過)というものです。
回答欄の右にある重要という欄について、少しご説明します。米国原版はもともと3項目基準と合わせて、6項目の重要項目基準を採用していました。日本版においては、対象年齢が若干米国よりも低いことを考慮して、パイロットスタディの結果をもとにこれらの10項目を日本版での重要項目とし、1歳6ヵ月健診の有用性研究に用いました5)。項目2「他児への関心」、項目6「要求の指さし」、項目7「興味の指さし」、項目13「動作模倣」、項目14「呼名反応」、項目20「耳の聞こえの心配」、項目23「社会的参照」です。
地域の大規模追跡研究の結果、3項目基準のみを採用しても、大きく結果に影響はないことがわかりました。
結果の解釈の仕方
基準としては、前述の3項目基準についてのエビデンスがありますが、実際は項目の数だけでなく、その内容にも注目することが大切です。神尾らの地域ベースの大規模追跡研究のデータ解析6)によると、項目6「要求の指さし」、項目13「動作模倣」、項目5「ふり遊び」、項目15「指さし追従」、項目21「言語理解」、項目9「興味ある物を見せに持ってくる」の6項目が、後のASD診断の識別力が高いことがわかりました。
地域での活用例
岐阜県本巣市では、乳幼児健診の機会を活用して、M-CHATの項目を「ままごとあそび」場面に工夫して取り入れ、子育て支援ツールとして活用していますのでご紹介いたします。実践するだけでなく、その成果について、コホート調査を通してエビデンスを検証し、真の社会実装をすすめている素晴らしい地域モデルです7)。こうした地域の実践とその実証的精査から、多くの地域でエビデンスに基づく切れ目のない支援システムの実装、そして全国への普及がすすむことを願っています。
おわりに
発達の問題のある子どもの養育にあたる親たちは、溢れる(しばしば誤った)情報に接して、どうすればよいのか不安に圧倒されて時間を過ごしています。そうしたケースに最初に出会う専門家は、M-CHATを適切に使って、エビデンスにもとづいた助言を行うことで、そうした親子が必要な支援につながりやすくなるでしょう。支援者自らの気づき、親の気づきを大切に、地域内の次の支援まで、伴走する際の根拠として役立ててください。
文献
- Robins DL, Fein D, Barton ML et al: The Modified Checklist for Autism in Toddlers: an initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. J Autism Dev Disord 31: 131-144, 2001.
- Inada N, Koyama T, Inokuchi E et al: Reliability and validity of the Japanese version of the Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT). Res Aut Spectr Disord, 5: 330-336, 2011.
- Inada N, Kamio Y, Koyama T: Developmental chronology of preverbal social behaviors in infancy using the M-CHAT: Baseline for early detection of atypical social development, Res Aut Spectr Disord 4: 605-611, 2010.
- Zwaigenbaum L, Bauman ML, Choueiri R, et al.: Early Intervention for Children With Autism Spectrum Disorder Under 3 Years of Age: Recommendations for Practice and Research. Pediatrics 136(Suppl 1), S60-81, 2015 doi: 10.1542/peds.2014-3667E.
- Kamio Y, Inada N, Koyama T, et al: Effectiveness of using the Modified Checklist for Toddlers with Autism in two-stage screening of autism spectrum disorder at the 18-month health check-up in Japan. J Aut Dev Disord, 44:194-203, 2014.
- Kamio Y, Haraguchi H, Stickley A et al.: Best Discriminators for Identifying Children with Autism Spectrum Disorder at an 18-month Health Check-Up in Japan. J Aut Dev Disord 45(12), 4147-4153, 2015.
- 別府悦子, 宮本正一編著, 神尾陽子監修. 子どもの社会的行動のアセスメント-早期発見と支援に生かせる乳幼児健診でのままごと遊び. 風間書房, 東京, 2023.4.28.
- 神尾陽子.: ASD アセスメントと診断.発達障害の診断と治療-ADHDとASD. pp 185-198. 榊原洋一, 神尾陽子編著,診断と治療社, 東京, 2023.4.28.
神尾陽子クリニック 院長/児童精神科医
お茶の水女子大学 客員教授
国立精神神経・医療研究センター精神保健研究所 客員研究員
神尾 陽子
問い合わせ先: kamio-yアットマークasd-dd.jp
※アットマークの部分を@に変更してください。