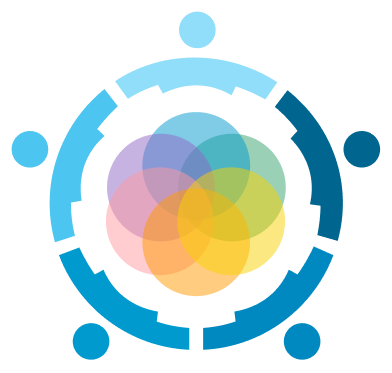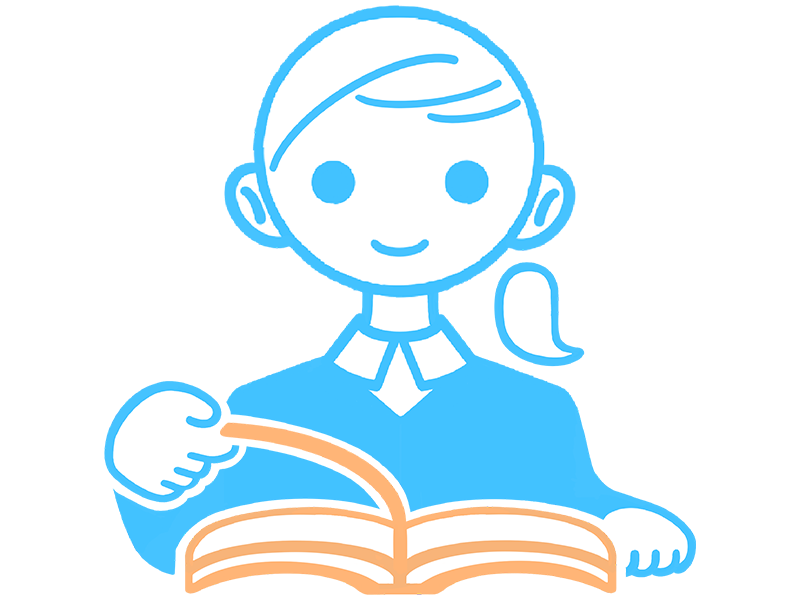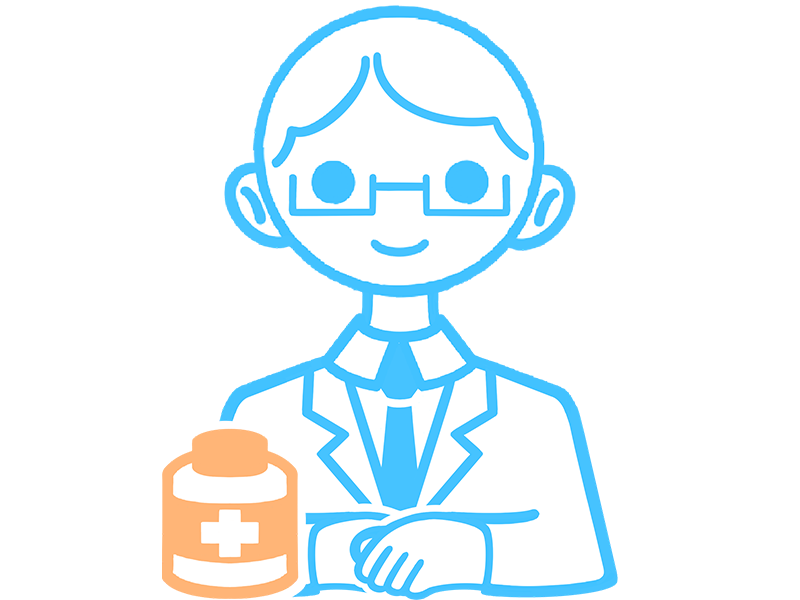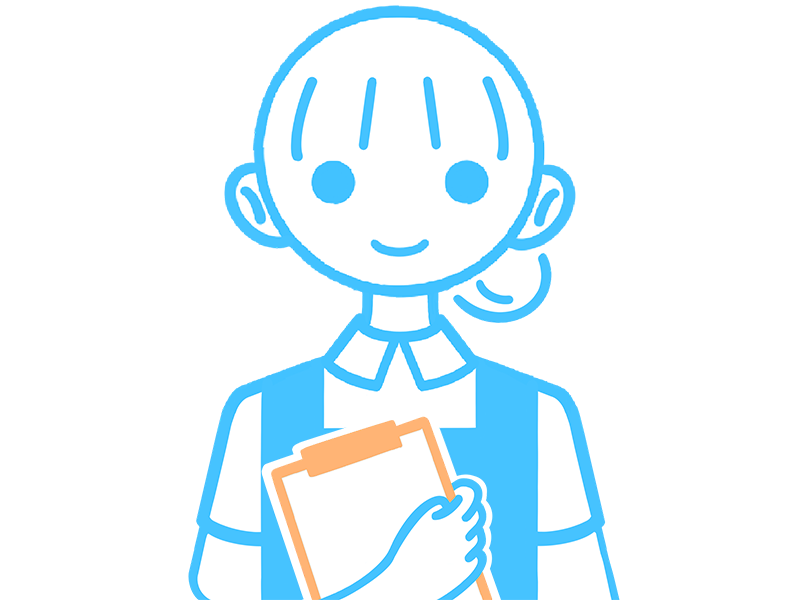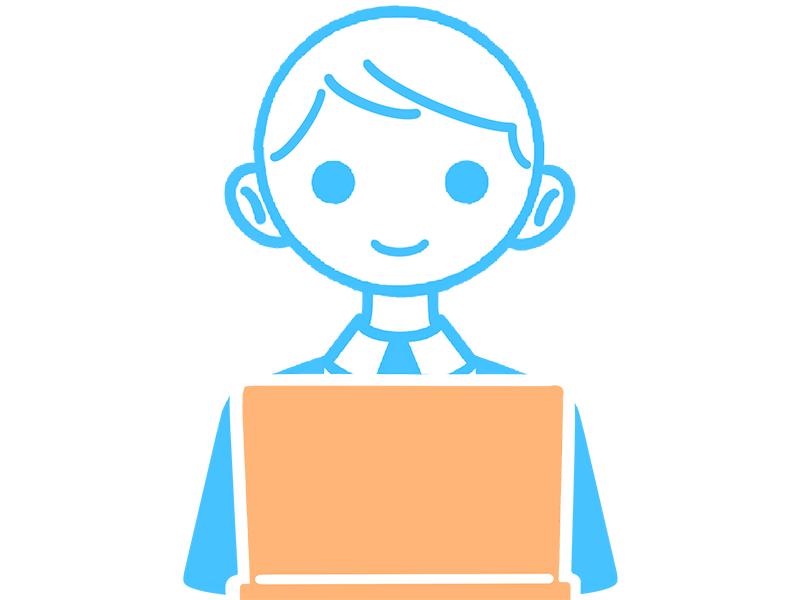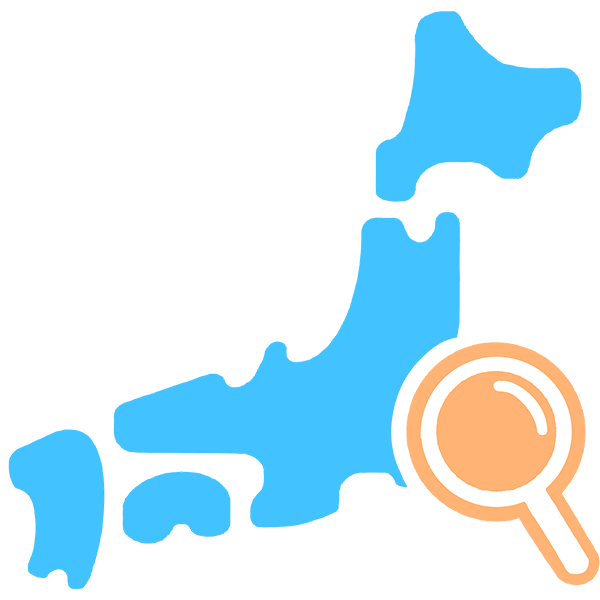お知らせ
研修コンテンツ集
トピックス
教育
発達障害のある児童生徒等への支援に向けた教育・福祉の連携事例集(文部科学省)
文部科学省では、教育と福祉が連携し、行政分野を超えた切れ目のない一貫した支援を進めていくため、教育・福祉の連携促進に取り組んでいる自治体にヒアリングを行い、 「発達障害のある児童生徒等への支援に向けた教育・福祉の連携事例集」を作成しました。
特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査
文部科学省で実施した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果(令和4年)」をご紹介します。
文部科学省では、通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査を平成24年に実施後10年が経過し、この間、発達障害を含め障害のある児童生徒をめぐる様々な状況の変化があったこと等を踏まえ、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態と支援の状況を明らかにし、今後の施策の在り方等の検討の基礎資料とするため、令和4年に本調査を実施しました。このたび、本調査の結果をまとめましたので、お知らせします。
本調査における「Ⅰ.児童生徒の困難の状況」については、学級担任等による回答に基づくもので、発達障害の専門家チームによる判断や医師による診断によるものではありません。従って、本調査の結果は、発達障害のある児童生徒数の割合を示すものではなく、特別な教育的支援を必要とする児童生徒数の割合を示すものであることに留意が必要です。
本調査は、平成14年調査、平成24年調査と対象地域や一部質問項目等が異なるため、単純比較することはできないことに留意が必要です。
通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果(令和4年)について[wp-svg-icons icon="new-tab" wrap="i"](文部科学省)
平成24年に文部科学省で実施した「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」をご紹介します。
本調査の結果は、発達障害のある児童生徒数の割合を示すものではなく、発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合を示すことに留意する必要があります。調査結果より、知的発達に遅れはないものの学習面または行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒の状況は、全体の6.5%存在することがわかりました。
通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査[wp-svg-icons icon="new-tab" wrap="i"](文部科学省)
発達障害のある児童生徒の生徒指導
.mb0{
margin-bottom: 0em; /* 行間 0 */
}
.mb1{
margin-bottom: 1.7em; /* 行間の1倍 */
}
.mb2{
margin-bottom: calc(1.7em * 1.5); /* 行間の1.5倍 = 約2.55em */
}
.hr1 {
height: 5px;
background-image: repeating-linear-gradient(45deg,#2589d0 0, #2589d0 1px, transparent 0, transparent 50%);
background-size: 5px 5px;
}
h3.custom {
font-size:1.3em;
padding: .5em .7em;
border-left: 5px solid #2589d0;
background-color: #f2f2f2;
color: #333333;
}
h4.custom {
font-size:1.2em;
padding:0 .4em .2em;
border-bottom: 3px dotted #2589d0;
background-color: #ffffff;
color: #333333;
}
ul.no-marker,ol.no-marker {
list-style: none !important;
margin: 0;
padding: 0;
}
ul.custom-list,ol.custom-list {
margin-bottom: 1.5em !important; /* リストの下に余白を追加 */
}
/* 念のため li 側もリセット */
ul.no-marker li {
list-style: none !important;
}
ul.no-marker li::before {
content: none !important;
}
p.indent {
padding-left: 3em; /* 全体を3文字下げる */
text-indent: -3em; /* 1行目だけ戻す */
}
p.indent2 {
padding-left: 1em; /* 全体を1文字下げる */
text-indent: -1em; /* 1行目だけ戻す */
}
p.setback {
padding-left: 1em; /* 全体を1文字分右にずらす */
}
p.setback3 {
padding-left: 3em; /* 全体を3文字分右にずらす */
}
li.indent{
padding-left: 3em; /* 全体を3文字下げる */
text-indent: -3em; /* 1行目だけ戻す */
}
「生徒指導提要」が改訂され、発達障害、精神疾患、健康、家庭や生活背景などについても「多様な背景を持つ児童生徒への生徒指導」として取り上げられました。
「生徒指導提要」とは、小学校段階から高等学校段階までの生徒指導の理論・考え方や実際の指導方法等について、時代の変化に即して網羅的にまとめ、生徒指導の実践に際し教職員間や学校間で共通理解を図り、組織的・体系的な取組を進めることができるよう、生徒指導に関する学校・教職員向けの基本書として作成したものです。
平成22年に初めて作成して以降、いじめ防止対策推進法等の関係法規の成立など学校・生徒指導を取り巻く環境は大きく変化するとともに、生徒指導上の課題がより一層深刻化している状況にあります。こうしたことを踏まえ、生徒指導の基本的な考え方や取組の方向性等を再整理し、今日的な課題に対応していくため、12年ぶりの改訂を行い、令和4年12月に公表しました。
生徒指導提要(改訂版)[wp-svg-icons icon="new-tab" wrap="i"](文部科学省)
国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターと国立特別支援教育総合研究所は、発達障害のある児童生徒の「生徒指導」や、発達障害の不登校リスクと予防についてわかりやすく解説した「生徒指導リーフS(Special Needs Education)」を共同で作成いたしました。
発達障害と生徒指導~自尊感情への配慮~(PDF:1.15MB)
不登校の予防~発達障害の特性と不登校リスク~(PDF:827.0KB)
「中1ギャップ」の真実~発達障害の特性等に応じた小中のつながり~(PDF:1.07MB)
「生徒指導リーフS」シリーズは、下記のページからもダウンロードできます。
国立教育政策研究所 生徒指導・進路指導研究センター[wp-svg-icons icon="new-tab" wrap="i"]
独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所[wp-svg-icons icon="new-tab" wrap="i"]
独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所 発達障害教育推進センター[wp-svg-icons icon="new-tab" wrap="i"]
発達障害と生徒指導(PDF:1.15MB)
不登校の予防(PDF:827.03KB)
「中1ギャップ」の真実(PDF:1.07MB)
医療・保健
小児期発症流暢症(吃音)
小児期発症流暢症(吃音)<Childhood-Onset Fluency Disorder /Stuttering>は、話し言葉が滑らかに出ない発話障害のひとつです。言葉を繰り返す、引き伸ばす、言葉がなかなか出ないという3つの症状が主です。ここでは吃音の特徴、吃音のある子への支援や合理的配慮等について説明します。
トゥレット症を含むチック症
チック症(<span lang="en">Tic Disorders</span>)は突発的、急速で反復的、非律動性(リズミカルではない)の運動あるいは発声を指し、通常は幼児・児童・思春期に始まります。 なかでも、多彩な運動チックと一つ以上の音声チックが1年以上続くものをトゥレット症(<span lang="en">Tourette’s syndrome</span>)と呼びます。
発達性協調運動症
発達性協調運動症(Developmental Coordination Disorder: DCD)は、神経疾患がないのに協調された運動スキルの獲得や使用が困難で、学校生活、遊びなどの日常生活活動を阻害している状態です。はさみや食器の使用、書字、スポーツがうまくできないなどに問題が生じやすいです。
福祉
発達障害者支援の新たな取り組みに関係する資料
発達障害者支援に関するモデル事業や、具体的な実践報告の場である「発達障害支援の地域連携に係る全国合同会議」の資料など、新しい好取組事例の紹介をしています。
発達障害に関する諸外国の動向と国際関係
「発達障害」という用語は、国や地域によって示す範囲が異なります。ここでは諸外国の実情と、日本に在住する外国人保護者向けに作成したパンフレットも紹介しています。
労働
障害のある方の就労に関する施策(障害者雇用促進法)
障害者雇用促進法に基づく、支援制度について説明します。企業の雇用担当の方にとっては最も気になるトピックです。支援制度について十分に理解し、企業支援などで生かしていきましょう。
障害者雇用・福祉連携強化プロジェクトチーム
令和元年7月、雇用施策と福祉施策の一体的展開の推進に係る諸課題について総合的に検討するため、厚生労働大臣を本部長とする「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」の下に設立されたプロジェクトチームです。これまでの取り組みや今後の動きなどについてご紹介します。