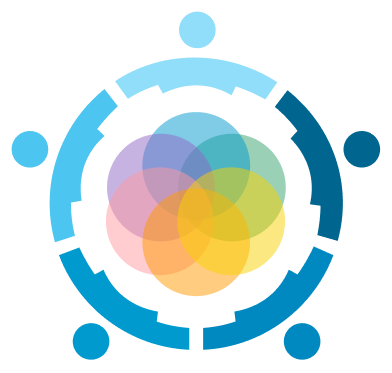医療・保健
小児期発症流暢症(吃音)
※本文では「吃音」と表記しています。
1.吃音の特徴:症状の過小評価の危険性
吃音は、言葉を繰り返す連発「ぼぼぼぼくは・・・」、引き伸ばす伸発「ぼーーーーくは」、言葉がなかなか出ない難発「・・・・ぼくは」という3つの症状が主です。これらの症状から養育者が吃音を強く疑い、支援者の元へ相談に行くことが多いでしょう。しかし、実際にそのお子さんと話しても、思ったほど吃音の症状が出ないことが多いです。その流暢に話す様子に、相談を受けた人がつい「気にならないですね」「軽い吃音ですね」という言葉をかけることは、養育者にとってプラスに働くことは少ないです。伴奏に合わせて歌ったり、2人で同じ言葉を言ったりする(外的なタイミングがある)場合に、吃音は消失し、流暢に話せるため、吃音は発話のタイミング障害と言われています。つまり、お子さんが気を付けて話すときには吃音があまり出ず、家庭などで自分の話したいことが思い浮かんだままタイミングを合わせずに話すときには、吃音が顕在化していると想像することが大切です。そして、吃音のメカニズムの説明は有用です。
2.原因論の変遷:養育者の味方の必要性
吃音の原因論として、「利き手を矯正したことが悪い」「吃音を親が意識させたことが悪い」「下の子が生まれて愛情不足が原因」「習い事のストレスが悪い」と、環境的な要因が原因であるとされ、特に養育者が原因とされる説が言われていた歴史的背景があります。しかし、双子研究では吃音の原因の約8割はその子の生まれ持った体質であることが示されており[1]、相談に来る養育者の味方となる必要があります。祖父母から母親の育児態度が責められていることもあるため、祖父母も交えた情報共有が必要です。
吃音は2歳から4歳の間に人口の約8~11%に発症します。しかも、発症の4割は急にある日始まることが知られています。そのため、「今まで流暢に話していたのに、何か悪いことをしたのではないか」と、子どもに吃音が始まったことを驚き、相談に来る場合があります。しかし、吃音の始まり方についての情報提供をすることが、養育者が我が子を客観的に見ることに役立ちます。
3.吃音のある子への支援
「なおるのか?」が養育者の最大の関心事だと思います。吃音を発症後、男児では3年で6割、女児では3年で8割が自然回復します。相談時に「将来、吃音はなおりますか?」と尋ねられても、「男児で家族歴がある場合は、なおりづらい」としか返答できない状況です。そのため、「この吃音とうまく付き合っていく方法を一緒に考えていきましょう」と、ともに吃音のある子を支援していく方針を伝えています。幼児吃音臨床ガイドライン第1版(2021)[2]には、Q15. 積極的な介入(月2回以上の指導)を行うタイミングは?として、A15. ①年少組までは経過観察的な支援を行うことを基本とする。②年中組では積極的な介入の開始を検討する。③年長組では積極的な介入の開始を推奨する。としています。
吃音の原因として生まれ持った体質によることが多いため、推奨グレードAにリッカム・プログラム(養育者が毎日決まった時間を子どもと設けて、子どもの発話に対して、褒める、確認するなどの返答を行う。吃音が出た時と出ていない発話の対応を専門家の指導のもと検討し、吃音のない発話を増やしていく)が紹介されていますが、非英語圏でのリッカム・プログラムには3倍の時間がかかることが示されており[3]、養育者の心情に配慮した対応が大切です。接し方については、幼児吃音臨床ガイドライン第1版(2021)と添付資料1から5に記載されているように、聞き手の姿勢の変化が必要とされています[2]。
【小学校以降の支援:毎年のリスクマネジメントの積み重ね】
吃音のある子どもは、発話場面でしか症状が出ないため、悩みが過小評価されることが多いです。他の子どもから話し方を真似されたり、笑われたり、「なんでそんな話し方なの?」と質問されることが多いです。担任の先生、養育者、支援者は、本人に「真似されていない?」「笑われていない?」「話し方を質問されていない?」とオープンに聞くことが、吃音の話をオープンにするきっかけとなります。学校では毎年クラス替えがあり、真似・笑い・質問を受けるリスクがあるため、早期発見とその対応法をオープンに話すことが予防につながります。また、日直の号令、音読、発表、かけ算の九九、学習発表会、卒業式などの特定の場面で困ることがあるため、より具体的に質問することが、困り感の早期発見につながります。
4.合理的配慮と福祉・支援サービス
養育者は持続する吃音に対して不安を感じるでしょう。しかし、吃音のセーフティネット体制を伝えることで、将来の見通しを持てる可能性があります。2024年に「改正障害者差別解消法」[4]が施行され、国公立の学校だけではなく、私立の学校も「合理的配慮」の提供が義務化されました。そのため、高校入試や大学入試での面接試験で、事前に吃音があることを伝えておくと、「過重な負担」[4]となる範囲を除き、寛容な聞き手の姿勢や時間的な余裕の確保など「合理的配慮」を受けることができます。また、入学後の修学上の困難に対しても、双方の建設的な対話の上に「合理的配慮」が受けられるようになりました[5]。吃音のある人は電話が苦手ですが、2021年から総務省が主体となり公共インフラの一つとなった「電話リレーサービス」[6]を吃音のある人が使うことができ、困り感の軽減につながっています。また、吃音症は精神障害者保健福祉手帳または身体障害者手帳の対象となるため、就職面接で障害者枠の選択肢も増えています[7-8]。
- 九州大学病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科 助教
- 菊池 良和
【参考文献】
- 1.Frigerio-Domingues C, Drayna D. Genetic contributions to stuttering: the current evidence. Mol Genet Genomic Med. 2017 Feb 19;5(2):95-102.
- 2. 森浩一. 幼児吃音臨床ガイドライン第1版(2021)と添付資料, 2021. (2024.12.23確認済) http://kitsuon-kenkyu.umin.jp/guideline/
- 3. Subasi M, Van Borsel J, Van Eerdenbrugh S. The Lidcombe Program for Early Stuttering in Non-English-Speaking Countries: A Systematic Review. Folia Phoniatr Logop.2022;74(2):89-102.
- 4.内閣府.リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html(2025.2.25確認済)
- 5.菊池良和. 吃音の合理的配慮. 学苑社, 2019.
- 6.総務省. 聴覚障害者等の電話利用の円滑化.
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/telephonerelay/(2025.1.28確認済)
- 7.菊池良和. 臨床ノート「精神障害者保健福祉手帳を取得し就職できた吃音患者の1例」耳鼻と臨床 67(4), 280-283, 2021.
- 8. 菊池良和. 臨床ノート「吃音症患者に対して身体障害者手帳を記載した2例」耳鼻と臨床 64(2), 72-75, 2018.