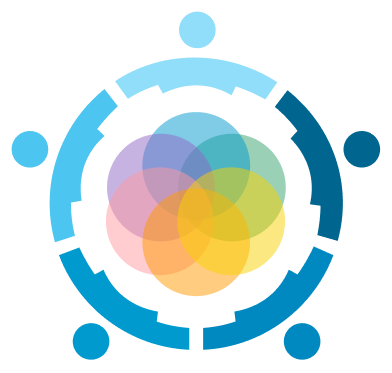教育
発達障害のある方の特性に応じた、教育での対応や制度などを支援者向けにご紹介します。
-

気づき
「発達」をみていく際にどのような点がポイントになるのかご紹介します。ライフステージごとの「発達」について知ることが、現在困っていることの解決につながるかもしれません。
-

特別支援教育の基礎知識
「特別支援教育」は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、そのもてる力を高め、生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導および必要な支援を行うものです。平成19年4月から、「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、すべての学校において、発達障害を含め障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。
-

特性の理解
発達障害は、発達障害者支援法において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。 「アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害」は、DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版)でなくなり、分類全体を示す「広汎性発達障害」は「自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害」に、「注意欠陥多動性障害」は「注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害」に変更されていて、ICD-11(疾病及び関連保健問題の国際統計分類 第11 版)も同様な方向となっています。本ページでは改訂された用語を用いています。(2021年7月23日掲載)
-

指導・支援
発達障害のある子どもへの指導・支援では、学習障害(LD)・注意欠如多動性障害(ADHD)・自閉症スペクトラム障害(ASD)のそれぞれの特性に応じた工夫が子どもの学びやすさ、生活のしやすさにつながります。その一方で、診断名の重複や変更、状態像の重なりが生じることもあり、その場合には診断名や特性を明確化することよりも、まず子どもの状態像から対応を工夫することが大切です。状態像を踏まえた指導・支援によって子どもの抱える困難さが軽減され、周囲による特性の把握や子どもの学びの充実につながることも十分に考えられます。 子どもの状態像は環境要因から大きな影響を受けます。合理的配慮と基礎的環境整備、教材・教具の工夫も大切な視点です。
-

合理的配慮と基礎的環境整備
障害のある子どもに対する支援については、法令に基づきまたは財政措置により、国は全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教育環境の整備をそれぞれ行う必要があります。これらは、合理的配慮の基礎となる環境整備であり、「基礎的環境整備」と呼ばれています。 合理的配慮は、「障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、「学校の設置者及び学校に対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とされています。
-

教材・教具データベース
障害のある児童生徒が、将来の自立と社会参加に向け、その能力を最大限発揮するためには、多様な学びの場において、障害の特性や状態を踏まえた教材を活用し、適切な指導を行うことが必要です。また、障害のある児童生徒の教材については、十分な教育を受けられるようにするための合理的配慮の充実をはかる上でも、国や地方公共団体においては、基礎的環境整備の一環としての教材の確保及び合理的配慮の一環としての教材の工夫が求められています。
-

教育と他分野との連携