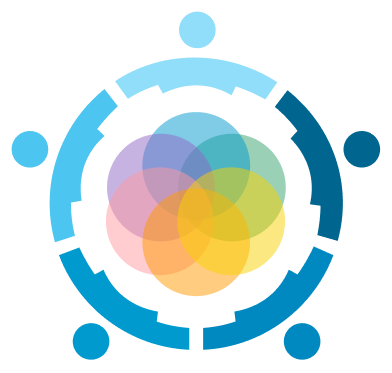医療・保健
自閉スペクトラム症
自閉スペクトラム症は、人生早期から社会的コミュニケーション及び対人的相互反応において持続的な困難があり、行動、興味、又は活動の限定された反復的な様式が認められる神経発達症の一つです。
成長とともに、感情のコントロールができるようになったり、社会的スキルを身につけることによって、自閉スペクトラム症の特性に伴う困難が軽減したりすることもありますが、基本的には生涯にわたってその特性はみられます。注意欠如多動症、限局性学習症、協調運動症、トゥレット症などの他の神経発達症や、うつ病、双極症、強迫症、不安症群などの精神疾患を伴う人もいます。
自閉スペクトラム症の原因は、遺伝と環境の相互作用とされています。複数の遺伝子、両親の年齢、低出生体重、低酸素、鉛暴露、妊娠中の母体感染症などの多様な要因が関係しており、子育ての結果によるものではありません。自閉スペクトラム症の状態像は、年齢によって異なります。
ライフステージごとにみられる状態
自閉スペクトラム症の乳幼児には、目と目を合わせる、指さしを行う、微笑み返す、後追いをする、模倣をする、人見知りをするなどといった社会的行動が弱かったり認められなかったりすることがあります。また、抱っこを好まない、なかなか寝つかない、偏食が激しい、自分のやり方へのこだわりが強く融通が利かないなど、保護者にとって子育てしづらいと感じることもあります。始語が遅く言葉の発達に遅れが認められる場合もあります。
保育所や幼稚園に入ると、保護者との分離が難しい、集団での遊びに参加したがらない、友達との適切なやりとりができない、給食では特定の食べ物しか口にしないことなどの特徴が認められることがあります。会話の場面においても、一方的になりやすく、相手の発言に耳を傾けることができなかったり、尋ねられた事柄に答えられなかったりします。また、自分が興味を持った特定の物事(例えば、特定の絵本や、電車・自動車、タブレットなど)に関しては、過度に熱中しやすく知識も豊富となる傾向が顕著です。初めてのことや、予定を変更されることは好まず、環境に馴染むのに時間がかかることがあります。
学童期には、一斉授業の中で担任の話を聞く、クラス全体に出された指示に従う、班で活動するなど社会集団行動が増えますが、そうした行動に苦痛を感じることがあります。また、読む、書く、計算するなどの学習が、学年が上がるにつれ困難になってくるお子さんもいます。
思春期になると、学校生活に適応するため、より高度で多様な対人スキルが求められることから、つらさを感じたり、また、いじめなどの被害に遭っても家族、先生、友達にうまく相談できなかったりすることもあります。そのため、出来るだけ早く本人の異変に気づけるよう、周囲の大人が、常に注意深く観察することが必要です。
成人後は、仕事が臨機応変にこなせないことや対人関係などの悩み、家庭生活や子育ての悩みを抱えることで、うつなどの精神的不調が増し、病院を訪れる人もいます。福祉的サポートを受けることで生活がしやすくなることがありますし、医療による支援が有効なこともあります。
支援について
幼少期には、個別療育や小集団での療育を通して、日常生活スキルの獲得やコミュニケ―ションスキル等の発達を促していきます。併行して、養育者に対しても、心理的サポートを行うとともに、子どもの特性の理解を深め、好ましい関わり方を身につけるための支援を行って、より良い親子関係が育めるよう促していきます。
学齢期には、特別支援教育とともに、放課後等デイサービス、移動支援などの福祉的支援が活用されています。近年では高等教育への支援も拡大しており、学生相談室に加えて、障害学生支援室における支援を提供している大学も認められます。また、発達障害者支援センターや地域生活支援センターなどでは、幅の広い相談対応、就労や生活自立に関する支援や情報の提供、障害者職業センターでは職業能力評価、ワークトレーニング、ジョブコーチの派遣等も行っています。
医療機関では、診断及び特性に応じた支援の一部が行われ、場合により薬物療法が実施されることもあります。しかし、現状において自閉スペクトラム症を根本治癒する薬物療法はなく、実施されるのは、かんしゃく症状などへの易刺激性に対する抗精神病薬(リスペリドン、アリピプラゾール)の投与、睡眠障害に対するメラトニンの投与です。そのほか、てんかんや精神症状等に対する薬物療法が実施されることもあります。
- 奈良県立医科大学精神医学講座 教授
- 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
- 精神保健研究所 知的・発達障害研究部 客員研究員
- 岡田 俊