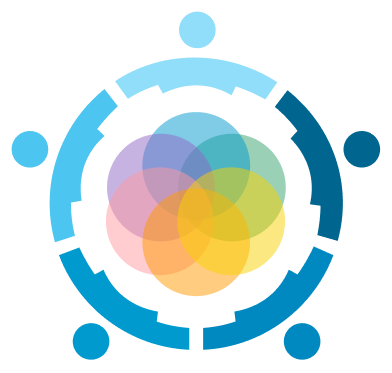学校保健
学校保健
学校保健では、学校において児童生徒などの健康の保持増進をはかるだけでなく、集団教育の場で学校教育活動に必要な健康や安全への配慮を行うこと、人々が自らの健康とその決定要因をコントロールし、改善することができるようにするプロセスであるヘルスプロモーションの考え方が導入されていて、自己の健康の保持増進だけでなく、まわりの環境に働きかけられる能力を育成することなどが行われます。これらを、学校における保健管理と保健教育と呼びます。また、学校には保健組織活動があり、校長、保健主事、養護教諭、教諭、学校三師(学校医、学校歯科医師、学校薬剤師)、栄養教諭、スクールカウンセラーがそれぞれの役割を果たしつつ、学校全体で組織的に活動しています。これらは、根拠である学校保健安全法、同法施行令、施行規則に基づいて運営されています。保健室の運営も、学校保健活動の中に位置づけられています。学校保健では、薬物乱用防止教育、依存症(行動嗜癖)に関する教育、心のケアに関する健康教育など、すべての児童生徒向けの活動を行っており、その中で発達障害についても学ぶことになります。
学校定期健康診断が毎年行われています。健康診断の場面だけでこころの問題を診断することは困難ですが、専門医への相談の必要性について判断することはできます。その際、こころの問題を大きく発達の問題(発達障害)、内在化問題(不安やうつなどこころの内側の問題)、外在化問題(いらいらして人や物に当たる攻撃行動が代表的であり、行動としての外側からみえる問題)に分けて捉えることも有用です。また、思春期に発症しやすい精神疾患(統合失調症、摂食障害など)にも留意します。
さらに学校保健について知りたいときは、公益財団法人日本学校保健会ホームページの精神保健・精神疾患の記述が参考になると思います。
【出典】
公益財団法人日本学校保健会.「児童生徒等の健康診断マニュアル」(p.100-101).
https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H270030/index_h5.html#100(外部サイト)
【参考資料】
文部科学省.「発達障害のある児童生徒等への支援について(通知)」.2005-04-11
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/gakuseishien/1290235.htm(外部サイト)