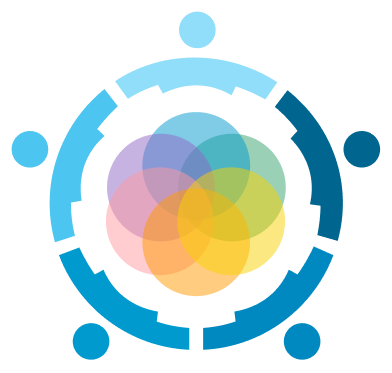余暇とは
発達障害のある方の余暇とは
発達障害に限らず、何かしら障害のある方たちの余暇とは、就労、学習、文化、スポーツなどと同様に社会参加の一つであり、自立の基礎となり得るものです。生活の質(QOL)を考えるとき、仕事のようにある一定の決められた時間以外の生活、余暇時間の過ごし方についても充実していることが大切です。
子どもの場合
子どもの発達過程において、幼児から低学年時期に一つのことに興味をもち、大人顔負けの知識を身につける子どももいます。その中には、さらに知識を深め、極めていく場合があります。その状況は発達のその後の段階で薄れていくことが多いですが、ライフワークや仕事になる場合もあります。子どもがみつけた興味・関心は尊重して受け止めてほしいのです。
たとえば、3歳のA君は、テレビやDVDのあるキャラクター怪獣が大好きです。すべての怪獣を覚えていて、基本の怪獣の進化後の怪獣名も全部言い当てるほどです。A君のお母さんは、「怪獣ばかり知っていても何の役にも立たない」と歓迎していないようです。しかし、A君は年齢があがっていくうちに、恐竜、その他の動物、昆虫の進化や変態にも興味をもち、名前だけでなく、その生態を知りたいと思うようになりました。A君のお母さんは、今度はとても嬉しく思いました。
このように大人が子どもの興味を受け止めることは、本人の肯定感を育てます。積極的な気持ちをもてるようになり、その後の余暇にもつながります。
子どもが興味・関心を抱く事柄はさまざまです。何に興味をもっているかを、注意深くみましょう。いろいろな環境を提供し、経験を広げていきましょう。3歳以上になれば、子ども同士が遊べる場所が必要です。幼稚園、保育園はとても興味の広がる場所です。個々の発達や特性に合わせて、児童発達支援事業所や児童発達支援センター、放課後等デイサービスなどの療育的な場も必要かもしれません。
大人の場合
思春期あたりから、興味・関心の示し方は変わってきます。育ってきた環境や培ってきた経験が大きく余暇の活動に影響します。子どもの場合と同様に、本人の興味・関心に対して肯定的に受け止めていくことが大切です。学齢期であれば、学校という場で友達やその他の大人とのやり取りの中で興味を広げていきやすいです。
発達障害のある方にとって、余暇活動を定期的な生活の一部にしていこうとしても、興味・関心だけでは、なかなか結びつかないことが多いです。興味の範囲が狭いこともありますが、生活の一部として取り入れることが苦手な場合もあります。実行するまでと定着するまでの行動を一つひとつ支援していくことが大切です。
知的障害をともなう発達障害のある方
余暇活動の広げ方は、基本的に「子ども」や「大人」の場合と同じです。子どものころは知的障害もあるので、その認知段階によっては粗大運動を中心とした遊びが好きだったり、本来の玩具の用途とは別の遊び方をしたりするかもしれませんが、周囲の大人は一つひとつ子どもが示す興味を受け止めて、その発達と情緒面に合わせて、できるだけひとりでの遊びと人と一緒の遊びを増やしていくことが大切です。年齢があがるにつれて、内容はさまざまですが、興味の広がりが出てきます。それによって、学齢期や大人になってからの仕事(作業)や余暇への取り組みが容易になります。
知的障害をともなう発達障害のある方にとって、活動に参加するための大きな問題として、認知段階にもよりますが、活動場所に行くまでの移動があります。ひとりの場合、少しでも興味があるものをみつけると寄り道してしまい、行けなくなることもありますので、支援者の案内が必要です。このような場合に、障害者総合支援法において、「行動援護」という移動の支援があります。詳しくは、以下を参照してください。
- 行動援護(厚生労働省)
発達障害のある方の余暇は、その人の状態や特性により、一般のサークルや趣味の活動の場が適していることが多いです、また、とても高度でプロに近い趣味の集まりは、発達障害のある方のよりどころとなる場合もあります。
発達障害のある方の余暇活動に関しての相談は、「相談」の項目をご参照ください。