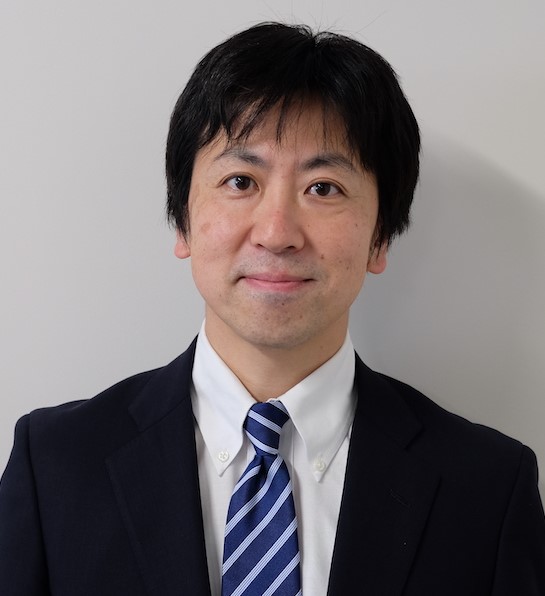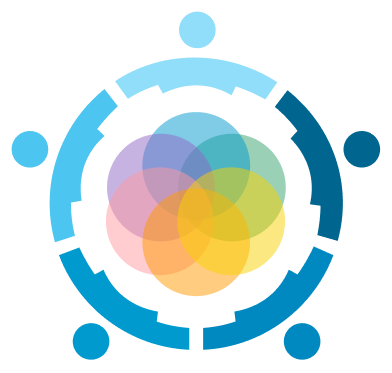関連記事
発達障害の子どもとスクリーンタイム~その1「卵が先か、ニワトリが先か」~
近年、子どもたちのスクリーンタイム(テレビやタブレット、スマートフォンなどの画面を見ている時間)について、保護者の方々から「長すぎるのでは」「発達に悪影響があるのでは」といった不安の声を多く聞きます。特に、発達障害のある子どもにおいては、その傾向が強いとも言われています。そこで今回は、最新の研究からわかってきたスクリーンタイムと発達障害の関係について、解説します。
発達障害と遺伝子との関係
まず、知っておいて頂きたいのは、代表的な発達障害であるADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)の原因は、遺伝子の小さな違い(両親から引き継ぐこともあれば自然に生じることもあります)と、出生時の環境要因が関係していると考えられていることです。つまり、生まれつきあるいは生まれた直後から、発達障害の特性が現れやすい体質がかたちづくられると考えられるのです。
スクリーンタイムと発達障害の関係
発達障害特性とスクリーンタイムに関連があることはこれまでにも繰り返し報告されてきましたが、「卵が先か、ニワトリが先か」、つまり「発達障害だからスクリーンタイムが長くなるのか、スクリーンタイムが長いから発達障害になるのか」については議論が続いていました。また、スクリーンタイムが成長と共にどう変化するのかについてもはっきり分かっていませんでした。
2023年に私たちの研究チームが発表した論文では、生後24ヶ月から40ヶ月の子どもたちを追跡し、どのようにスクリーンタイムが変化していくかを調べました。その結果、スクリーンタイムは、初めから最後まで短いグループ、初めから最後まで長いグループ、だんだん長くなるグループなどに分かれることが分かりました。そして、ASDと関連する遺伝子の小さな違いを多く持つ子どもほど、初めからスクリーンタイムが長くなりやすく、ADHDと関連する遺伝子の小さな違いを多く持つ子どもでは、成長とともにスクリーンタイムが長くなる傾向が見られました。
つまり、長時間スクリーンに触れているから発達障害になるのではなく、もともとそうした傾向のある子どもが、結果としてスクリーンに強く惹かれやすいという可能性があると言えます。この点について、2024年に私たちが発表した総説論文でも、複数の研究成果をふまえて詳しく論じています。
では、なぜ彼らはスクリーンに惹かれるのでしょうか? ADHD傾向のある子どもは、強い刺激やテンポの速い映像に注意が引きつけられやすく、次々と変わる映像が心地よく感じられることがあります。一方、ASD傾向のある子どもは、人とのやりとりよりも、視覚的な刺激やパターン化された情報に安心感を覚えることが多く、結果としてスクリーンを好むことがあります。
ゲームに惹かれる子どもたちの特徴
また2025年の研究では、3歳から9歳までの子どもたちのゲーム時間の変化を追跡し、ゲーム時間が年齢とともに顕著に増加していく子どもたちがごく一部存在することがわかりました。このグループに属する子どもたちは、ADHDと関連する遺伝子の小さな違いを多く持つ子どもたちでした。これらの結果から、ゲームに夢中になる背景には、個人の特性が関連していることが見えてきます。
ゲーム時間が増加して行くグループの子どもたちは、対人関係や感情の調整に困難を抱えていました。ただ、ゲーム時間が長いからそのような問題が生じるのか、そのような問題を抱えているからゲームに向かってしまうのか、については、今後の研究が必要です。
「まず減らす」より「理解する」が大切
スクリーンタイムが長すぎることが発達に悪影響を与えるのではないかと、保護者の方はご心配かもしれませんが、一方で、発達障害のある子どもにとって、スクリーンやゲームは「安心できる場所」「コントロールできる世界」として機能していることがあります。一律に「減らす」「禁止する」のではなく、「なぜ惹かれているのか」「代わりに何ができるか」を考えることが、より実りある支援につながります。ゲームについては止めやすいタイミングもあります。お子さんと一度一緒にゲームをやってみるのも良いかもしれません。
人との交流や外遊びの機会を増やす
さらに、きょうだいが多い子どもや、外での遊びや人とのやりとりが多い子どもほど、スクリーンタイムが短い傾向があることも分かっています。これは、社会的な関わりが自然とスクリーンの代わりになることを示しています。保護者の方にとっては、子ども同士の交流の場をつくることや、安心して遊べる環境を用意することが、スクリーンタイムとの付き合い方を見直す手がかりになるかもしれません。
<さらに詳しくお知りになりたい方へ>
- https://www.ncnp.go.jp/topics/detail.php?@uid=AHD8MXaHe7BUZvuW
「国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(NCNP)」ホームページ
参考文献
- - Takahashi et al., Psychiatry Research, 2023
- - Takahashi et al., European Neuropsychopharmacology, 2025
- - Takahashi & Tsuchiya, Frontiers in Psychiatry, 2024
- 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
- 精神保健研究所 知的・発達障害研究部 部長
- 髙橋 長秀