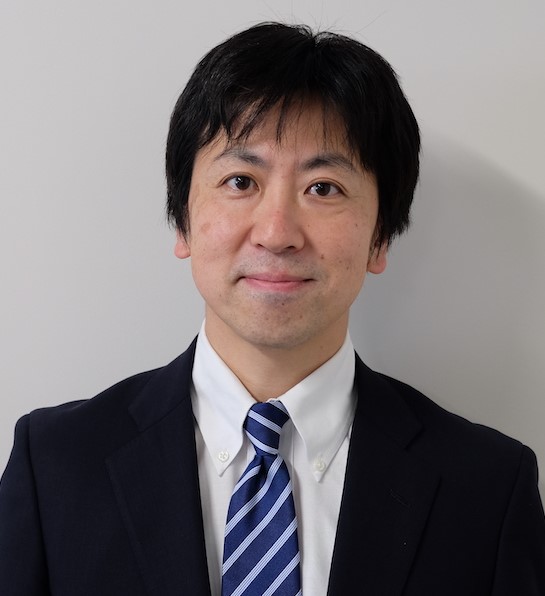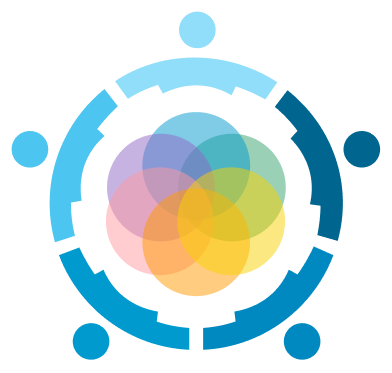関連記事
発達障害の子どもとスクリーンタイム~その2「睡眠との関係」~
スクリーンタイムの睡眠への影響
その1でお話ししたように、ADHDやASDなど発達障害の傾向をもつ子どもたちは、一般的にスクリーンを見る時間が長くなる傾向があります。スクリーンを見る時間が長くなると、特に夜間の使用によって睡眠時間が削られたり、寝つきが悪くなったりするなど、睡眠リズムが乱れてしまうことがあります。スマートフォンを至近距離で見ることで、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑えられてしまうことも知られています。その結果、「夜ふかし」や「睡眠の質の低下」が起こって、結果として「日中の落ち着きのなさ」、「集中困難」、「かんしゃくや不機嫌」が強くなるというケースがあるのです。
このように、スクリーンタイムの延長は、間接的に睡眠を通じて行動に影響を及ぼす可能性もあるため、「どの時間帯に・どのような内容を・どれだけ見るか」にも注意を向けて、親子で無理のないようにスクリーンタイムをコントロールすることが大切です。
「上手に眠れない子ども」もいる
一方で、発達障害の特性の強い子どもの中には、体質的に上手に眠れない子どもがいることも分かってきました。ASDの子どもは感覚過敏が強く、ちょっとの音で目が覚めてしまったり、そもそも寝付けなかったりする子も少なくありません。ADHDの子どもでは、メラトニンが上手く分泌されないことでリズムが崩れやすく、寝つきや寝起きが悪くなることもあります。
日本でも、メラトニンが医薬品として販売されています。スクリーンタイムや生活習慣を見直しても上手く眠れない時には、医療機関に相談してみるのもよいでしょう。眠れない子がいる家庭では、家族が疲弊してしまうということも知られています。
「寝るのが遅い」ことでADHDと誤解されることも
ADHDは「落ち着きがない」「話を聞いていない」などの行動から、幼稚園や学校で指摘されることが多い発達障害です。しかし、最近の研究では、ADHDであるか否かに関わらず、「夜ふかし」や「睡眠の質の低下」が「落ち着きのなさ」や「注意の散漫さ」などを引き起こしていることも分かってきました。
2022年に私たちが行った研究では、約800人の子どもたちを対象に、睡眠の状態と行動との関係を調べました。その結果、夜10時以降に寝る子どもは、「落ち着きのなさ」や「注意の散漫さ」が強く見られることが明らかになりました。
これは、本当はADHDではないのに、「夜更かし」によってADHDの特性に似た行動が現れることで、ADHDと誤解される可能性がある、ということを示しています。
睡眠の見直しが症状の軽減につながる可能性がある
実際に、睡眠の習慣を整えることで、「朝起きられるようになった」「園での集中力が上がった」といった変化が見られる子どももいます。「かんしゃくや不機嫌が減った」という声も聞きます。どのお子さんにとっても、睡眠の習慣を整えることはとても大切なことなのです。
<さらに詳しくお知りになりたい方へ>
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8733839/
「アメリカ国立医学図書館(National Library Medicine)」(英語、外部サイト)
お子さんの「困りごと」に気づいたときに大切なこと
「最近、落ち着きがない」「話を聞いていないことが多い」「かんしゃくが増えた」、そんなお子さんの様子に、保護者の方が「もしかして発達障害かもしれない…」と不安を抱えることは少なくありません。
まずは専門家に相談することが大切です。保護者だけで抱えこまず、医療機関や相談機関で評価を受けることで、お子さんの特性が明らかになり、必要な支援や配慮につなげることができます。
そのうえで、私たちがぜひ知っていただきたいのが、「生活リズムや環境の整え方も、お子さんの行動に大きな影響を与える」ということです。たとえば、夜更かしや睡眠不足があると、日中の集中力が下がり、ADHDのような行動が目立ってしまうことがあります。また、長時間のスクリーン使用が睡眠に影響し、感情の安定にも影響するケースもあります。
このように、「専門家への相談」と「生活の見直し」はどちらも大切です。お子さんの「困りごと」の背景を多角的に見つめていくことで、よりよい支援のヒントが見えてくるはずです。
発達障害の診断は“ゴール”ではなく、“理解とサポートのスタートライン”です。必要な支援につながるためにも、まずは信頼できる専門家にご相談ください。
参考文献
- - Takahashi et al., JAMA Network Open, 2022
- - Takahashi et al., Psychiatry Research, 2023
- - Takahashi et al., Psychiatry Research Communications, 2024
- 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター
- 精神保健研究所 知的・発達障害研究部 部長
- 髙橋 長秀