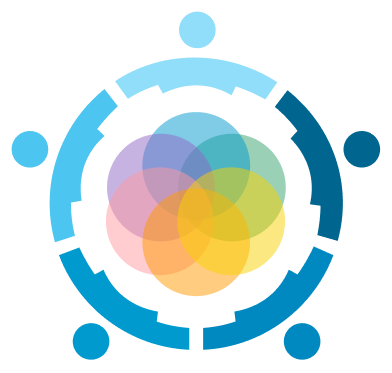関連記事
聴覚障害と自閉スペクトラム症の関係ー語用論の視点からー 【後編】
4.発達障害への示唆
語用論的な発達
語用論的な能力の発達プロセスは、言語発達との相互作用で捉えられてきました。ASD児の子の心の理論課題の成績は言語指標との相関が報告されています。また、聴覚障害児の心の理論の発達においては、とくに他者とのやりとりの経験が重要であることが示唆されています。
アメリカの大規模調査で、Schick et al.(2007)は、ろう児を、アメリカ手話で育つネイティブサイナー児と、非ネイティブサイナー児、口話で育つろう児にわけて、一次誤信念課題を調べています。その結果、親がろう者のネイティブサイナー児は聞こえる典型発達の子どもと差がなく、親が聴者の非ネイティブサイナー児は7歳頃キャッチアップし、音声言語を得ようとしている子は、この3群のなかでは成績が悪いという結果が出ています。こののち学齢期のろう児を対象にした心の理論課題に関する研究では、自分以外みな聞こえる子どもたちに囲まれた環境で育つろう児は、ネイティブサイナーであっても二次誤信念課題などを含むスコアが、典型発達より低く、手話を使う子どもたちに囲まれているろう児より悪いという結果も出ています(Meristo et al. 2016)。ただし、手話を使うろう児に囲まれているネイティブサイナーはろう難聴児の中でも少数派で、一般化には注意が必要です。
聴覚障害児とASDの語用論的発達は言語発達との相互関係が問題
日本では、2019年より難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクトが開始され、聴覚障害児の特別支援教育にあたる文部科学省と、早期療育を担当する厚生労働省が連携して検討を進めてきました。主に近年の医療・補聴技術の進展を背景に、早期発見と早期療育開始、聴覚特別支援学校と言語聴覚士などとの連携について議論が進んでいます。補聴器や人工内耳で音声言語の獲得を促す方向の支援については議論が進展しましたが、重度難聴児の3〜4割に上る重複障害について、まだ議論が進んでいないようです。そのうち、語用論的発達が問題になるのは、ASDとの重複ですが、それがASDそのものなのか、言語発達からの語用論的発達の環境が乏しいからなのかの鑑別は現在まで難しいです。
ASDでも類似のことがあり、de Villiers & de Villiers (2014)は、心の理論に関する社会性の発達の遅れにより、言語発達が遅れるだけでなく、言語発達が遅れるから心の理論課題がうまく理解できないという双方向の影響があることを示唆しています。最近は感覚の弱さによって言語音の隣接ペアが聞き分けられていないことも示されつつあり(Matsui et al. 2022)、言語の音声知覚と社会性による意味・意図理解どちらの要因がボトルネックになっているかなどを分析して、個別の支援に生かせる可能性もあります。
語用論レベルでの言語運用は、相手の意図を推論する能力と、前提を多く共有していることと、その場で通じ合った感覚を共有できることに支えられています。聴覚障害があって、聴者のコミュニティで生活や仕事をしていると、前提知識の共有について、抜けや漏れが発生します。聴者との会話でのお互いの意図のズレを察知するには、より多くの知識と、それを俯瞰する力、そして相手の意図を推論する力が必要になります。
ASDでも同様に、知覚の面での困りごとがある場合、聴覚障害と似たことが起こっている可能性があります。また、ことばが出ない、遅れるなどによって、周囲とのやりとりの経験が少なくなることによっても、会話文化が身につかず、語用論的な発達に影響があるでしょう。元々、ASDの語用論の障害についてはa〈意図の推論〉に注目されがちでしたが、生得的な意図理解能力の低さだけでなく、それを取り巻く知覚的な状態や、やりとりの経験、文化の習得などにも注目して、コミュニケーションの苦手さを評価し、フォローする方略が構築されるとよいでしょう。
聴覚障害とASDの重複
最後に、聴覚障害でASD様の症状を呈している人々については、言語ができないのか、意図推論に問題があるのか、その両方なのか、評価が難しくなります(中野 2016 for review)。本人が手話でも話していると、手話ができない支援者は、「音声言語では問題があっても手話では問題がない」と問題を過小評価してしまうかも知れません。手話でのやりとりで問題があることは、手話が流暢に扱え、分析的にその発話を評価できる手話教師にしか扱えません。加えて、言語の習得開始時期もこの心の理論(他者の意図理解)に影響することがわかっているため、言語が遅れたために発達障害様の様相を示しているのか、発達障害があったから言語習得が遅れたのかの因果関係もあとから推定するのが難しいです。聴覚障害がある子どもが音声言語を話していても、語用論的な発達が定型発達と異なり、かつそれぞれの子で様子が異なるために、明確な基準を作ることも難しいです。
言語が9歳レベルで止まってしまうという「9歳の壁」で、言語の支えを元にした抽象的理解ができないという話もありますが、このなかに「言葉尻を捉えて、一貫性なく人を責めたりする」ということが指摘されています(脇中 2013)。これも一種の社会性の欠如とみなされていますが、言語での談話構築能力も、相手のことばを全体で理解できない(言葉尻を捉えてしまう)ことも、文法能力と語用論能力の発達に関係があります。語用論的な能力の発達を踏まえ、「個人の能力を最大にする」言語を選ぶときに、社会の主流派言語である音声日本語だけでなく、語用論能力の発達に必要な、相手の言っている形式的要素を見落とさない環境(手話を使うなど)でのやりとりの経験は重要な要素と認識される必要があります。
参考文献
Baron-Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a “theory of mind”?. Cognition, 21(1), 37-46.
de Villiers, J. G., & de Villiers, P. A. (2014). The role of language in theory of mind development. Topics in Language Disorders, 34(4), 313–328.
Ferguson C.A. (1968) ‘Absence of Copula and the Notion of Simplicity: A Study of Norman Speech, Baby Talk, Foreigner Talk, and Pidgin’, Paper given at the Conference on Pidginization and Creolization of Language, Kingston, Jamaica. (retrieved from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED030844.pdf)
Fujino, H., Fukushima, K., & Fujiyoshi, A. (2017). Theory of mind and language development in Japanese children with hearing loss. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 96, 77–83.
Happé, F. G. (1995). The role of age and verbal ability in the theory of mind task performance of subjects with autism. Child development, 66(3), 843-855.
Happé, F. G. (1997). Central coherence and theory of mind in autism: Reading homographs in context. British journal of developmental psychology, 15(1), 1-12.
Jolliffe, T., & Baron-Cohen, S. (1999). A test of central coherence theory: linguistic processing in high-functioning adults with autism or Asperger syndrome: is local coherence impaired?. Cognition, 71(2), 149-185.
Jolliffe, T., & Baron-Cohen, S. (2000). Linguistic processing in high-functioning adults with autism or Asperger's syndrome. Is global coherence impaired?. Psychological medicine, 30(5), 1169-1187.
前田浩 (2021). 聴覚障害者の就労をめぐって[前編]—当事者の発信力を高める支援—. ろう教育科学, 62(3), 107-115.
Marschark, M., & Knoors, H. (2012). Educating Deaf Children: Language, Cognition, and Learning. Deafness & Education International, 14(3), 136–160.
Matsui, T., Uchida, M., Fujino, H., Tojo, Y., & Hakarino, K. (2022). Perception of native and non-native phonemic contrasts in children with autistic spectrum disorder: effects of speaker variability. Clinical Linguistics & Phonetics, 36(4-5), 417-435.
Meristo, M., Strid, K., & Hjelmquist, E. (2016). Early conversational environment enables spontaneous belief attribution in deaf children. Cognition, 157, 139–145.
中野聡子(2016)聴覚障害と自閉症スペクトラム障害. 手話学研究 25, 3-16.
Norbury, C. F. (2005). The relationship between theory of mind and metaphor: Evidence from children with language impairment and autistic spectrum disorder. British journal of developmental psychology, 23(3), 383-399.
Schick, B., De Villiers, P., De Villiers, J., & Hoffmeister, R. (2007). Language and theory of mind: A study of deaf children. Child development, 78(2), 376-396.
脇中起余子. (2013). 「9歳の壁」を超えるために―生活言語から学習言語への移行を考える―. 北大路書房.
吉岡佳子. (2013). 日本手話におけるポライトネス. 手話学研究, 22, 3–36.
- 国立障害者リハビリテーションセンター研究所
- 高次脳機能障害研究室 流動研究員 高嶋 由布子
- [E-mail]takashima-yufuko(アットマーク)rehab.go.jp
- ※上記の(アットマーク)の部分を@に変更してください